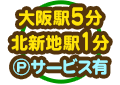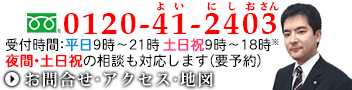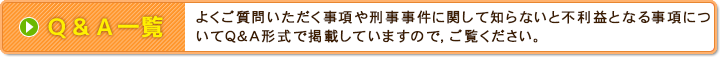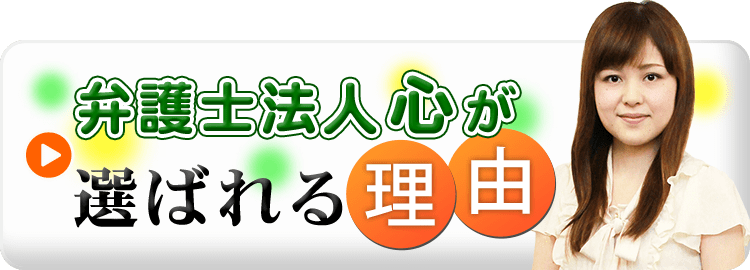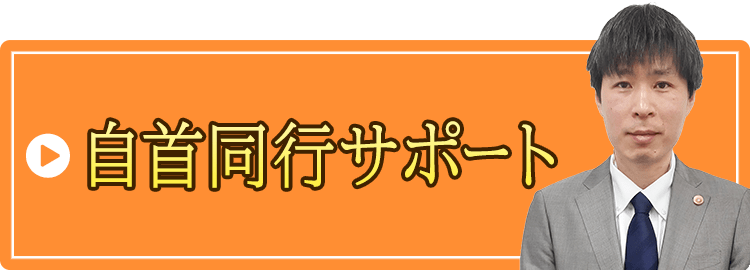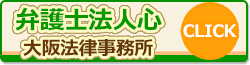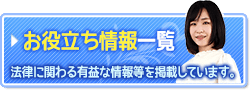「その他」のお役立ち情報
税理士が犯罪をしたらどうなるのか
1 税理士の欠格事由
税理士が罪を犯した場合には、犯罪ごとに規定された刑罰を受けることになります。
その上、税理士の資格を失う可能性があります。
税理士の資格について規定した税理士法4条は、税理士の資格を欠くとみなされる要件である欠格事項を規定しています。
同条3号で、国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により拘禁刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの、
同条4号で、国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの、
同条5号で、国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの、
について、「税理士となる資格を有しない」と規定しています。
そのため、罪を犯して欠格事項に該当することになれば、税理士の資格を失うことになります。
なお、執行猶予付きの判決を受けてそれが確定した場合でも、拘禁刑以上の刑に処せられたことは変わりないので、やはり欠格事由に該当し、税理士の資格を失うことになります。
2 税理士の再登録について
先ほど述べたとおり、刑の執行を終えてから3年ないし5年が経過すると、欠格事由に該当しないことになります。
また、執行猶予付きの判決を受けてそれが確定した場合でも、執行猶予期間が経過すると、刑の言渡しの効果が将来にわたり消滅します。
ですので、執行猶予期間が経過した時点で、拘禁刑以上の刑に処せられた者ではなくなり、欠格事由にも該当しないことになります。
だからといって、再び税理士登録を請求するとしても、登録がみとめられるとは限りません。
税理士法24条は、税理士登録の拒否事由を規定しています。
そのうち、同条7号ロは、税理士の欠格事由に該当していた者が登録の申請をした際、「税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者」は、「税理士の登録を受けることができない」と規定しています。