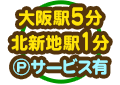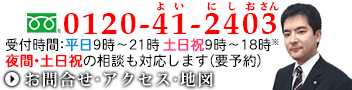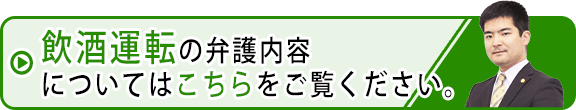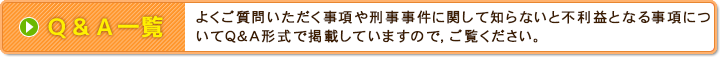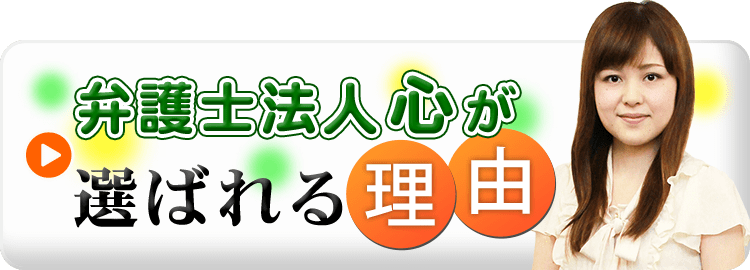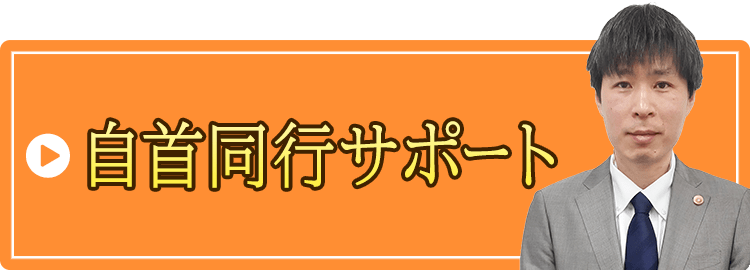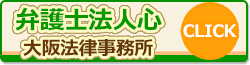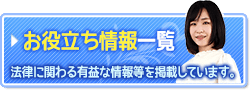「交通犯罪」に関するお役立ち情報
自転車での飲酒運転の処罰
1 自転車での飲酒運転の規制
自転車の運転も、自動車やバイクの運転と同じように、道路交通法により規則が定められています。
道路交通法65条1項は、自転車を含め、酒気を帯びて車両を運転することを禁止しています。
2 自転車での飲酒運転の処罰
自動車を酒気帯び運転した場合、道路交通法違反として処罰の対象になります。
しかし、自転車を酒気帯び運転したとしても、それだけでは処罰の対象にはなりません。
自転車を酒気帯び運転して処罰の対象になるのは、その運転をした場合において酒に酔った状態、すなわち酒酔い運転をした場合に限られます。
ここでいう「酒に酔った状態」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します。
どのような状態が「酒に酔った状態」なのかについて、呼気1リットル当たりのアルコール保有量などの明確な基準があるわけではありません。
これについて、道路交通執務研究会編著、野下文生原著・執務資料道路交通法解説は、「社会通念上、いわゆる酒に酔っぱらっている状態はもちろん、その程度に至らなくても、感覚機能、運転機能、判断力又は抑制力が著しくおかされている場合は、『酒に酔い』に該当するものと解してよいであろう。しかし、『酒に酔う』というのは、個人差が大きいので、具体的にそれぞれの場合について判断すべきものであると解する。」と述べ、事件ごとに個別的、具体的に「酒に酔った状態」かどうかを判断すべきとしています。
そして、「酒に酔った状態」の判断については、呼気1リットル当たりのアルコール保有量だけではなく、飲酒した量や時間、飲酒による影響の有無や程度、すなわち立っていられるか、歩けるか、呂律が回っているかなどから、判断されることになります。
先ほど述べたとおり、自転車を酒気帯び運転したとしても、それだけでは処罰の対象にはなりませんが、酒気を帯びて自転車を運転すること自体、交通取締りの対象になりますし、自転車の酒酔い運転の疑いがあるとして逮捕される可能性もあります。
自転車であっても、飲酒した後の運転はしないようにしてください。