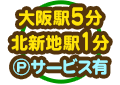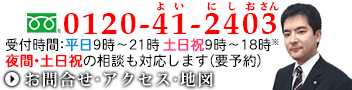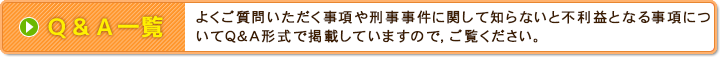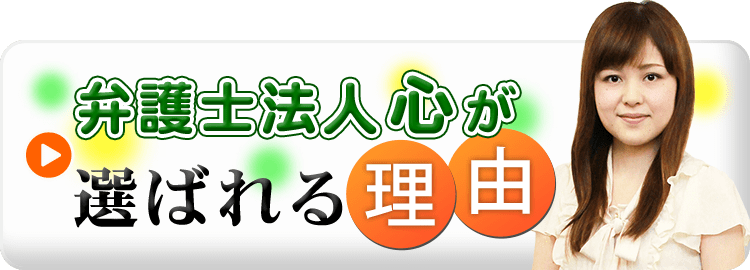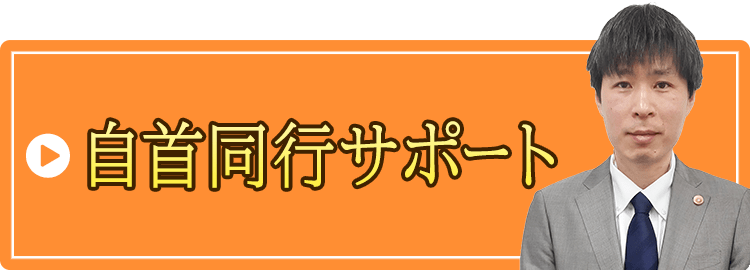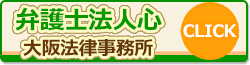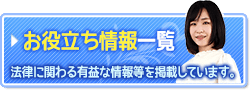「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
不起訴と無罪の違いとは
1 不起訴と無罪
「不起訴」「無罪」という言葉は、刑事ドラマ等でも用いられることがある言葉で、多くの方が聞いたことがあるかもしれません。
今回は、よく聞く言葉であるけれど、実際にはどのような違いがあるのか、「不起訴」「無罪」という言葉を簡単に解説したいと思います。
2 不起訴とは
日本の刑事司法においては、被疑者を起訴するか不起訴とするかの判断は、原則、検察官の専権事項とされています。
そのため、不起訴とは、基本的には、検察官によって被疑者を起訴しないという判断がなされたことを意味します。
不起訴の主な理由として、起訴猶予、嫌疑不十分等があります。
このうち、起訴猶予は、犯罪の嫌疑が十分認められて、有罪の証明ができるにもかかわらず、起訴しない判断をくだす場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分は、犯罪の嫌疑はあるものの、有罪の証明をするためには証拠が不十分であるために起訴しない判断をくだす場合の理由とされます。
3 無罪とは
無罪とは、被告人に対して罪を認めない裁判所の判断のことをいいます。
検察が提出した証拠では被告人を有罪とするのに十分ではないとき、無罪の判断を行います。
4 不起訴と無罪の主な違い
不起訴と無罪では、判断者が異なります。
不起訴の場合には検察官、無罪の場合には裁判官が判断をします。
また、不起訴の場合は、裁判自体がありませんが、無罪は、裁判をしたうえでの判断になります。
5 不起訴・無罪のご相談は弁護士法人心へ
不起訴、無罪は、判断者や裁判の有無等の違いがあるにせよ、被疑者・被告人にとって有利な内容であることには変わりありません。
もっとも、日本の司法においては、無罪を獲得することができるケースはごく僅かであり、基本的には不起訴を目指す弁護活動が主流になるでしょう。
特に、起訴されて有罪になると資格を喪失してしまうなどの場合には不起訴を目指す弁護活動が重要になります。
大阪にお住まいで、不起訴の弁護活動のご相談は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご連絡ください。
前科が付いた場合の公務員の資格制限 刑の減軽がなされるケース