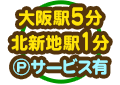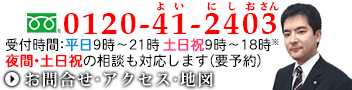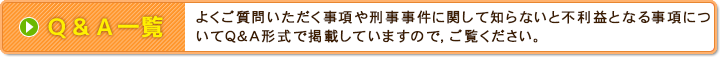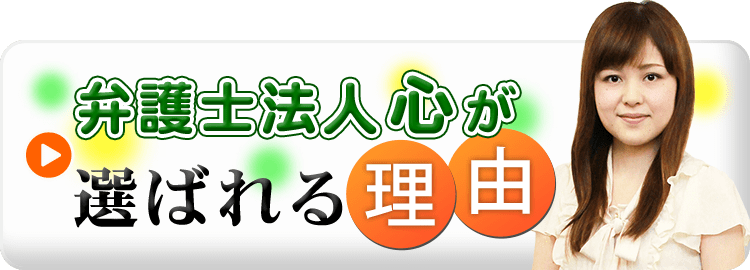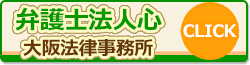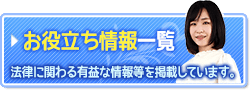「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
前科が付いた場合の公務員の資格制限
1 前科とは
確定判決で有罪とされ、刑の言渡しを受けた経歴のことを前科といいます。
前科は、正式な裁判で懲役刑や禁錮刑、罰金刑等の言渡しを受けた場合だけでなく、略式請求により罰金刑の略式命令を受けた場合でも付きます。
もっとも、前科は、起訴されなければ付けられないものです。
2 前科による公務員の資格制限
公務員が何らかの罪を犯し、確定判決で刑の言渡しを受けると、その公務員には前科が付くこととなります。
国家公務員法や地方公務員法により、公務員に前科が付いた場合、言渡しを受けた刑が懲役刑や禁錮刑であれば、公務員になる資格を失い、当然失職すると定められています。
さらに細かく見てみると、言渡しを受けた懲役刑や禁錮刑が実刑であれば、その刑の執行が終わるまで、公務員になる資格を失います。
また、言渡しを受けた懲役刑や禁錮刑に執行猶予が付された場合であっても、刑の執行猶予期間が終わるまでは、公務員になる資格を失うこととなります。
つまり、刑の執行を終えるか、刑の執行猶予期間が終わるかすれば、再び公務員を志望して試験を受けることは可能ですし、民間企業を志望して就職試験を受けることも可能だといえます。
もっとも、いずれの場合でも、前科が付いていることが採用の際に不利な事情となることは避けられないと考えられます。
3 公務員が資格制限を受けない場合と前科
一方、言渡しを受けた刑が罰金刑であれば、資格を失わないため、当然に失職することはありません。
ただし、その場合も、公務員にふさわしくない非行があったとして、懲戒処分がなされる可能性があります。
懲戒処分には、重いものから、免職、停職、減給、戒告があり、非行が相当に悪質とされれば、免職の懲戒処分を受けることがあります。
免職の懲戒処分を受けた場合、失職します。
失職した場合に再び就職を目指すこともできますが、懲役刑や禁錮刑の言渡しを受けて資格を失った場合と同じように、前科があることが採用の際に不利な事情となることは避けられないと思われます。