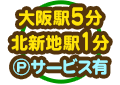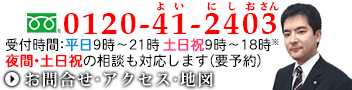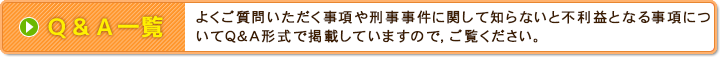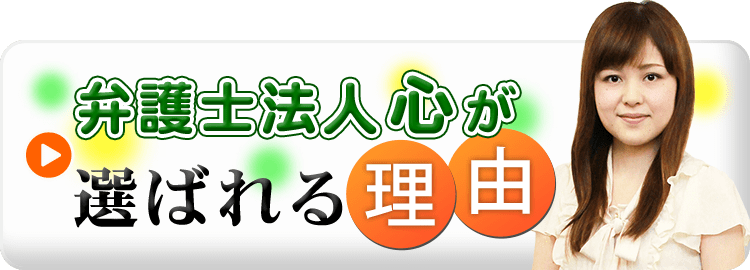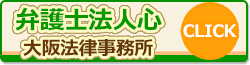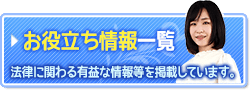「示談」に関するお役立ち情報
刑事事件で示談ができない場合の対応
1 刑事事件における示談の重要性
刑事事件を起こしてしまったことに争いがない場合、被害者の方と示談ができているか否かは、非常な重要なポイントとなります。
被害者の方と示談ができていると、例えば、逮捕や勾留といった身体拘束を回避できたり、不起訴となって刑事裁判にならなかったり、起訴されたとしても刑の減軽や執行猶予といった結果を獲得することができたりする可能性が高まります。
2 示談をするための流れ
被害者と示談をするためには、通常、弁護士を通して、警察官や検察官に示談をしたいという意向があることを伝え、被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を行っていくことになります。
被害者の方に示談に応じる意向があれば、示談金の額、被害届や告訴状を提出しないようにしてもらえるか、加害者を許すという意思を表示してもらえるか等について話し合いをし、示談書を取り交わします。
示談書の取り交わしが完了したら、示談書をコピーして、示談が成立した証拠として捜査機関に提出します。
3 示談に応じてもらえなかった場合の対応
示談交渉を行ったものの示談が成立しない場合や、そもそも被害者の方に示談に応じる意向がなく示談に応じてもらえないという場合も少なくありません。
そのような場合の対応方法として、「供託」と「贖罪寄付」についてご紹介いたします。
⑴ 供託
被害者の方が示談金の受け取りを拒否しているという場合は、示談金に相当する金額を法務局に「供託」するという方法が考えられます。
簡単に言うと、示談金を法務局に預けるというイメージです。
供託をすることにより、加害者側に示談金を払う意思があるということを示すことができますが、当然に法務局が供託を受け付けるわけではありません。
⑵ 贖罪寄付
また、示談が成立しなかった場合には、弁護士会等へ「贖罪寄付」をするという方法もあります。
贖罪寄付とは、被害者との示談ができない刑事事件等について、刑事手続の対象となっている方の改悛の情を表すための寄付のことであり、犯罪被害者の方などの救済のために用いられ、弁護士会なども受け付けています。
警察の取調べと検察の取調べの違い 刑事事件における示談と刑事和解との違い