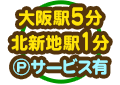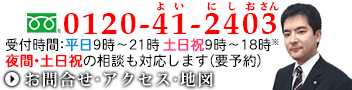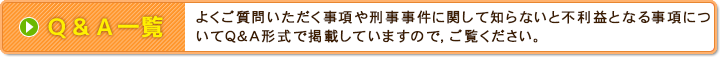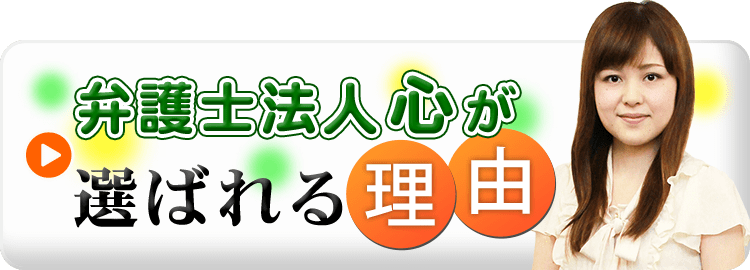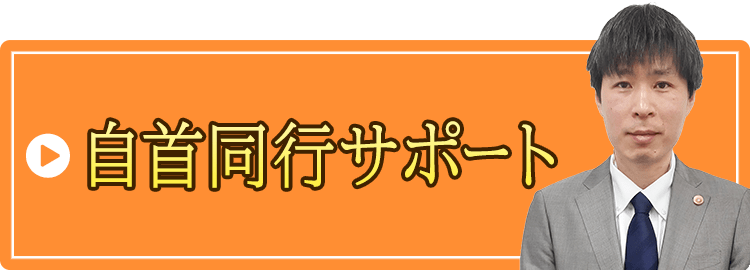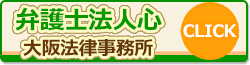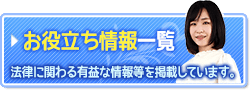「刑事裁判」に関するお役立ち情報
刑事裁判の流れ
1 冒頭手続き
刑事裁判の手続きの流れについて、ご説明します。
まず、裁判官から、被告人に対して人定質問が行われ、被告人が人違いでないことが確認されます。
その後、検察官が起訴状を朗読し、公訴事実と罪名、罰条が読み上げられます。
それを受けて、被告人は、裁判官から黙秘権の告知を受けた上、検察官が読み上げた公訴事実について意見を求められます。
通常、被告人は、公訴事実について間違いがあるかないかを述べます。
続いて、弁護人が、公訴事実について意見を述べます。
通常、弁護人は、被告人と同意見である旨意見を述べることが多いです。
2 証拠調べ
証拠調べの初めに、検察官は冒頭陳述を行い、証拠によって証明しようとする事実を明らかにします。
なお、弁護人も、必要があれば、裁判所の許可を受けて冒頭陳述をすることがあります。
検察官は、冒頭陳述の後で、証拠調べを請求します。
弁護人は、請求された証拠について同意、不同意等の意見を述べます。
それを受けて、裁判所が証拠調べの決定をします。
検察官は、証拠調べの決定があった書面の内容を朗読又は要旨の告知をするほか、証拠物を展示するなどして、証拠調べを行います。
弁護人も証拠調べを請求することがあります。
その際は、検察官が請求された証拠について意見を述べ、裁判所が証拠調べの決定をした後、弁護人が書面の朗読や証拠物の展示等を行います。
証拠調べ請求の際、証人尋問を請求し、裁判所が証人尋問の決定をすれば、証人尋問が行われます。
通常、証人尋問は、検察官か弁護人のうち、請求した方から先に質問し、続いて相手方、最後に裁判所が質問します。
通常は、証拠調べの最後に、被告人質問が行われます。
被告人質問は、弁護人、検察官、裁判所の順に行われます。
3 裁判の終結
証拠調べが終わった後、検察官と弁護人はそれぞれ意見を述べます。
その際、検察官は、求刑として、被告人に適切と考える刑罰を述べます。
一方、弁護人は、被告人の無罪を主張する場合はその旨述べ、有罪であることを争わない場合は、執行猶予付きの判決を求めるなど、被告人に寛大な処罰を求める内容を述べます。
最後に被告人が意見を述べ、結審します。
結審した後、裁判所から判決が言い渡されます。
判決は、裁判手続が終わって即日言い渡される場合もあれば(例外的です。)、判決期日を設定してその日に言い渡される場合もあます。
判決言渡しの日から14日以内に控訴がないならば、被告人が言渡しを受けた判決が確定します。