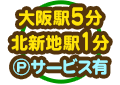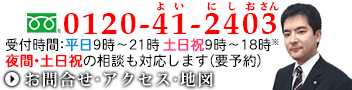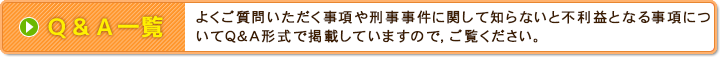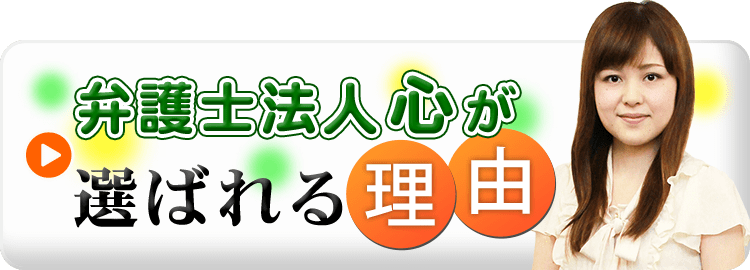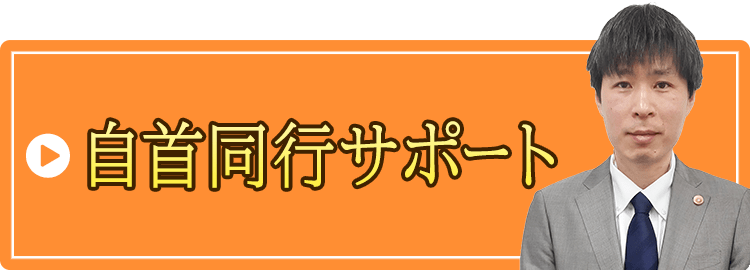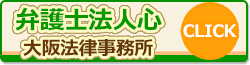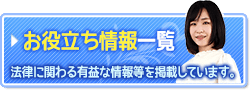「保釈」に関するお役立ち情報
保釈に関する手続の流れ
1 保釈について
保釈は、保釈保証金を納めることで拘束中の身柄が釈放される手続のことをいい、刑事事件における身柄拘束を解く手段の一つです。
公判請求された後も身柄拘束が続いているときに行われます。
2 保釈請求
保釈の請求は、勾留されている被告人又はその弁護人及び法定代理人らが行うことができますが、多くの場合、弁護人が保釈請求を行っています。
通常、弁護人は、①被告人に権利保釈の除外事由がないことや、②被告人に裁量保釈が認められる事由があることを主張して、保釈を請求します。
①の権利保釈は、保釈のうち、刑事訴訟法で規定された除外事由にあたらなければ認められるものをいいます。
刑事訴訟法では、権利保釈の除外事由として以下の項目が規定されています。
- ・ 一定の重大な罪を犯した場合
- ・ 過去に一定の重大な罪について有罪判決を受けた場合
- ・ 常習として一定以上の重さの罪を犯した場合
- ・ 証拠を隠滅するに足りる相当な理由がある場合
- ・ 被害者や証人に危害を加えるおそれがある場合
- ・ 氏名又は住所が明らかではない場合
弁護人は権利保釈を求める際、被告人にはこれらの除外事由がないことを主張します。
また、②の裁量保釈は、上記の権利保釈の要件を満たしていなくても、裁判所が適当と認めるときに許可されるものをいいます。
裁判所が裁量保釈を許可する際は、
- ・ 被告人に、同居している家族や身元を保証する人物がいることや、その者が被告人を逃走させないことを約束していること
- ・ 被告人が重い病気にかかっており、入院させる必要があること
- ・ 被告人が自営業者であり、資金繰りが極めて悪化していること
- ・ 被告人が受験生であり、志望校の受験が間近にあること
- ・ 被告人が弁護人と綿密な打ち合わせをする必要性があること
- ・ 被告人が介護している親族がおり、その生活が成り立たないこと
などの事情が考慮され得るものとされています。
3 釈放までの流れ
保釈の請求があった後、裁判所は、保釈を許す決定又は保釈を却下する決定をする前に、検察官の意見を聴きます。
その後、裁判所は、保釈を許すか却下するかの決定を行います。
そして、裁判所の決定に対しては、不服を申し立てることができます。
ですので、もし保釈が却下された場合でも、その決定に不服を申し立て保釈の決定をし直すように求めることができるのです。
保釈を許す決定がなされる際、保釈保証金の額が決められる他、住居を制限するなどの条件が付されます。
そして、決められた額の保釈保証金を裁判所に納めることにより、釈放されます。
保釈保証金の金額は、被告人や事件によって様々ですが、おおむね150万円から300万円程度になることが多いです。
逮捕・勾留されている家族と面会する際の注意点 保釈金の準備の仕方