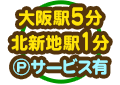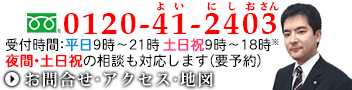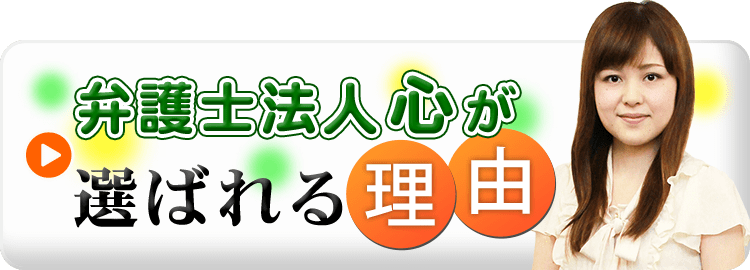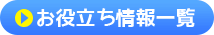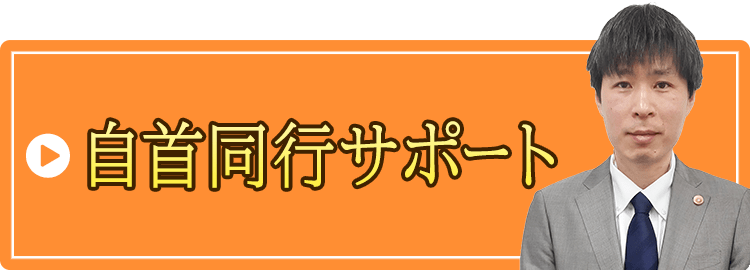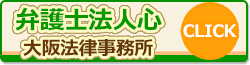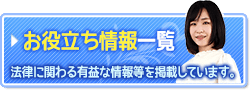詐欺
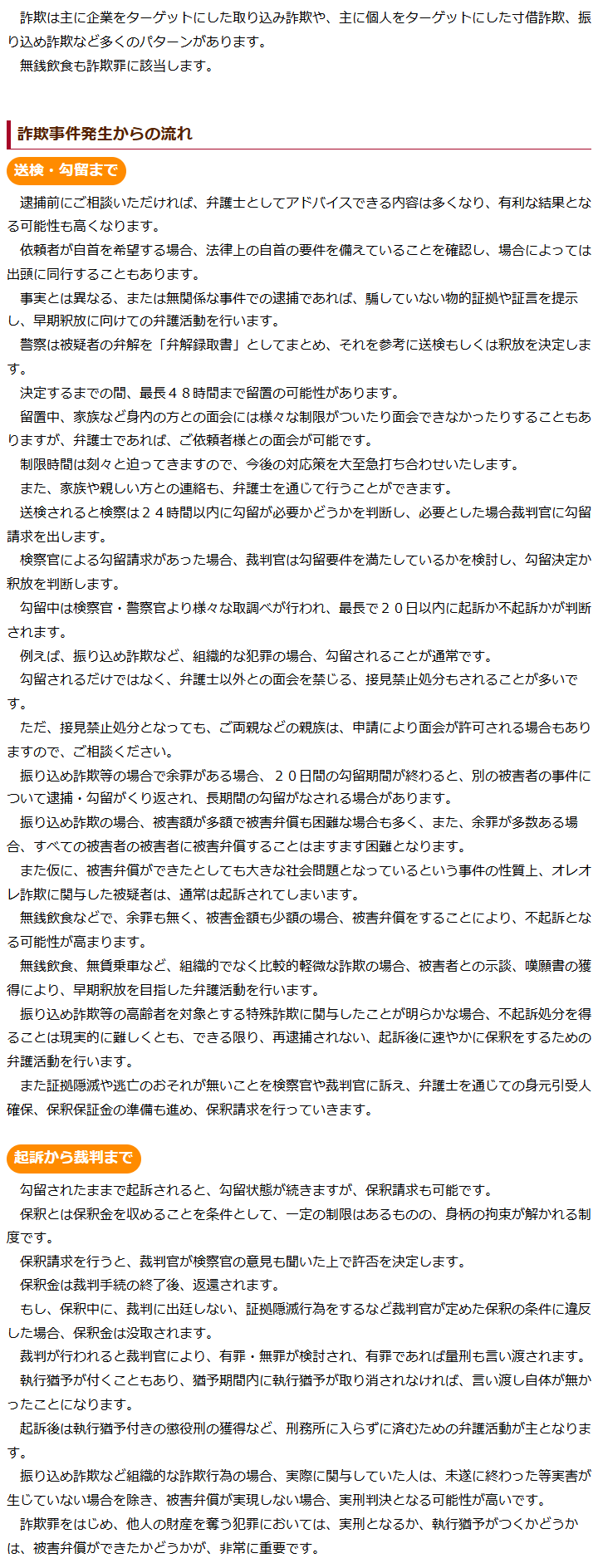
詐欺罪の成立要件とは
1 詐欺罪の行為

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる行為を処罰するものです。
この行為を細かく分けると
①相手方をだます行為
②だます行為によって相手方が現実に錯誤に陥ること
③錯誤に基づいて財物を処分する行為
④その処分行為によって財物が交付され、行為者又は第三者が財物を手に入れること
に分けることができます。
また、詐欺罪が成立するには、先ほど挙げた①②③④の行為が、相当な因果関係の範囲内にあることが必要です。
2 相手方をだます行為
例えば、無銭飲食や無銭宿泊だと、支払の意思がないのに人をだます意思で飲食物を注文し、あるいは宿泊の申込みをする行為が、相手方である店員をだます行為に当たります。
また、釣銭が本来受け取る金額より多額であることに気づいたのに、そのまま釣銭を受け取ってその場を立ち去る行為は、相手方である釣銭を渡した人をだます行為に当たります。
そして、いわゆるクレジットカード詐欺だと、クレジットカード会員が、代金支払いの意思も能力もないのに、自己名義のクレジットカードを使用して、加盟店から物品を購入する行為が、相手方である加盟店をだます行為に当たります。
さらに、いわゆる特殊詐欺だと、掛け子と言われる電話をかける役が、警察官や銀行員などを名乗って緊急に現金が必要となったなどと嘘をつき、受け子と言われる受取役に現金やキャッシュカードなどを手渡すように申し向ける行為が、相手方である電話をかけた相手をだます行為に当たることになります。
3 機械は錯誤に陥らない
もっとも、詐欺罪は、人の錯覚を利用する犯罪ですので、本来人に向けて行われる犯罪であって、機械を相手にしてだますような行為をしたとしても、相手方をだます行為には当たりません。
そのため、他人名義のキャッシュカードを勝手に使って現金自動預払機を操作して現金を引き出す行為や、金属片を使って自動販売機から商品や現金を取り出す行為は、相手方をだます行為がないので、詐欺罪には当たりません。
ただし、窃盗罪には当たる可能性があり、犯罪にはなり得ます。